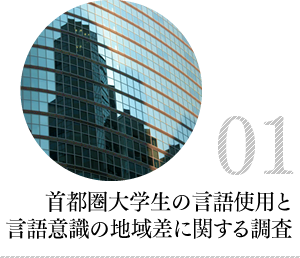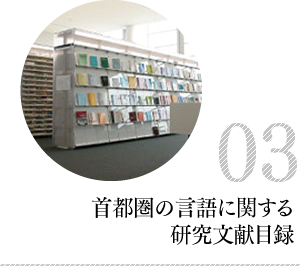東京語アクセント資料
現代東京語でアクセントのゆれが予想された12,803語について、年齢、地域(山の手と下町)、性別に偏りのないように考慮して選ばれた19名の話者のアクセント型を、個人別に記載した資料。他に、準備段階でアクセントをチェックした2名の話者と、4種のアクセント辞典記載のアクセント型が併記されている。共通語アクセントの基盤である現代東京語アクセントの、多様性の実態を明らかにすることを目的に作成された。調査は1982年から1984年にかけて実施。
調査語は次の手順で選定された。まず、山の手出身の若年層(1955年生まれ)男性1名と、下町出身の高年層(1920年生まれ)女性1名が、『新明解国語辞典』第3版(1981、三省堂)所収のアクセントが付された80,846語をすべてチェックし、三者でアクセントが一致しない17,518語を抽出した。ここから日常比較的よく用いられる語を中心に選び、さらに、他の辞典等から語を補った。したがって本資料の調査語は、調査時点においてアクセントにゆれのある日常語のかなりの部分を網羅したものである。
19名の話者の出身地の条件は、5歳から15歳までの間東京都区内で生育し、両親とも乙種アクセント地域の出身者とされた。生年は1911年から1962年まで。社会的活躍層という観点から、調査時20歳代から50歳代の話者が中心である。現在および今後の共通語アクセントの基盤としての東京語アクセントの担い手、ということが重視されていると言える。
作成の経緯の詳細は、原著「まえがき」(pp.3-10)参照。
調査語は次の手順で選定された。まず、山の手出身の若年層(1955年生まれ)男性1名と、下町出身の高年層(1920年生まれ)女性1名が、『新明解国語辞典』第3版(1981、三省堂)所収のアクセントが付された80,846語をすべてチェックし、三者でアクセントが一致しない17,518語を抽出した。ここから日常比較的よく用いられる語を中心に選び、さらに、他の辞典等から語を補った。したがって本資料の調査語は、調査時点においてアクセントにゆれのある日常語のかなりの部分を網羅したものである。
19名の話者の出身地の条件は、5歳から15歳までの間東京都区内で生育し、両親とも乙種アクセント地域の出身者とされた。生年は1911年から1962年まで。社会的活躍層という観点から、調査時20歳代から50歳代の話者が中心である。現在および今後の共通語アクセントの基盤としての東京語アクセントの担い手、ということが重視されていると言える。
作成の経緯の詳細は、原著「まえがき」(pp.3-10)参照。
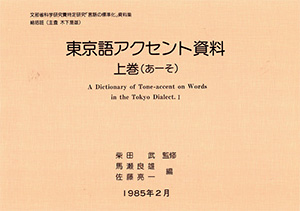
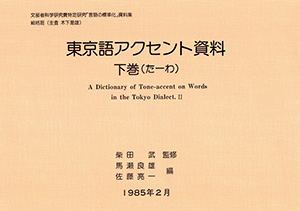
A Dictionary of Tone-accent on Words in the Tokyo Dialect
上・下2冊。柴田武監修,馬瀬良雄・佐藤亮一編。1985年刊行。
文部省科学研究費特定研究「言語の標準化」資料集。
ダウンロード
| PDF版 | データ版 | 調査票 |
|
(国立国語研究所学術情報リポジトリ) 東京語アクセント資料 上巻(あ-そ) 東京語アクセント資料 下巻(た-わ) 研究情報部分のみ抜粋(19ページ) 資料提供者・研究協力者・序・まえがき・凡例 PDF(6.35MB) |
Excelデータ ダウンロード XLSX(3.8MB) | 調査票ダウンロード(全24ファイル) ZIP(209KB) |
|
・このPDF版を引用する際は、次のように表示してください。 柴田武監修,馬瀬良雄・佐藤亮一編(1985)『東京語アクセント資料』(文部省科学研究費特定研究「言語の標準化」資料集;PDF版,国立国語研究所,2013年) |
・このデータを引用する際は、次のように表示してください。 柴田武監修,馬瀬良雄・佐藤亮一編(1985)『東京語アクセント資料』(文部省科学研究費特定研究「言語の標準化」資料集;データ版,国立国語研究所,2013年) |
・このデータを引用する際は、次のように表示してください。 柴田武監修,馬瀬良雄・佐藤亮一編『東京語アクセント資料』調査票(データ版,国立国語研究所,2013年) |
|
※ファイルサイズが大きいため、ダウンロードに時間がかかる場合があります。 上巻139.21MB 下巻156.45MB |
・原著上下2冊(pp.1-1028)のデータをExcel形式で電子化したものです。 ・入力に際して、通用の字体に改めた文字があります。 ・データ版には、原著にはない次の一連番号が付されています。 ページ:原著のページ 見出し番号:「見出し」の通し番号 語形番号:同じ「見出し」の中での「語形」の通し番号 回答番号:同じ「見出し」「語形」の中での回答の通し番号 ・その他の表の見方は、原著「凡例」(pp.11-17)を参照してください。 |
・調査時に使用した調査票の調査文をテキスト形式で電子化したものです。
調査票ごとに1ファイル。toacc1からtoacc24まで24のファイルに分かれています。
・原調査票は、B4判31行の罫紙を横長に使用、縦書き上下2段、手書き。全24編。 1調査票あたり基本的に600調査文。ただし調査票によって多寡があります。 ・その他、調査票については、原著「まえがき」(pp.6-7)を参照してください。 ・入力にあたり次のような処理をしました。 1.原調査票の傍線部(=調査対象語) →[ ]で囲む 2.原調査票のふりがな →漢字の直後に( )で囲んで表示 例:28 [内海(うちうみ)]は波が静かだ。(TOACC04) 3.通用の字体に改めた文字がある。 4.その他の主な入力に際しての変更点、注意点を各ファイル末の「入力注」に記載した。 |
電子版について
編著者の承諾を得て、国立国語研究所 共同研究プロジェクト「首都圏の言語の実態と動向に関する研究」(プロジェクトリーダー:三井 はるみ)で電子化を行い、公開するものです。また、原著に収められていない調査文の電子化を行い、併せて公開します。調査票原本は、澤木幹栄氏、相澤正夫氏から提供していただきました。
電子化と公開をご承諾いただき、ご協力くださった関係者のみなさまに、感謝いたします。
研究
この資料の分析から、(1) 多くの単語にアクセント型の年齢差、辞典との差が認められるという実態(馬瀬・佐藤1989,佐藤1990)、(2) 従来指摘されていた、尾高型の衰退、前部が起伏式の複合動詞の中高型化といった変化が、語としては拍数の長い語から、人としては山の手出身の女性から進行しているという変化プロセス(相澤1992,1996)、(3) 各地方言で受容されている共通語アクセントは、東京語でゆれのある場合、社会的活躍層で優勢な型と一致すること、などが明らかにされた。なお、語数が多い反面、話者数が限定されているという点について、佐藤(1996)は、都内1地域での多人数調査の結果から、ごく少数の語を除き、この資料が都区内のアクセントの実態を反映していることを確認している。
参考文献
相澤正夫(1992)「進行中のアクセント変化 ―東京語の複合動詞の場合―」国立国語研究所編『研究報告集』13相澤正夫(1996)「語の長さとアクセント変化 ―『東京語アクセント資料』の分析―」国立国語研究所編『研究報告集』17
佐藤亮一(1990)「現代東京語のアクセント ―年齢差および辞典との差を中心に―」佐藤喜代治編『国語論究第2集 文字・音韻の研究』明治書院
佐藤亮一(1996)「『東京語アクセント資料』の検証 ―下町多人数調査結果と比較して―」言語学林1995-1996編集委員会編『言語学林1995-1996』三省堂
馬瀬良雄・佐藤亮一(1989)「東京語アクセントの多様性」杉藤美代子編『講座日本語と日本語教育2 日本語の音声・音韻(上)』明治書院
「首都圏言語」プロジェクト・メンバー一覧
国立国語研究所 萌芽・発掘型共同研究プロジェクト「首都圏の言語の実態と動向に関する研究」(2010年11月~2013年10月)